絵やイラストのタイトルどう決める?良い例と悪い例
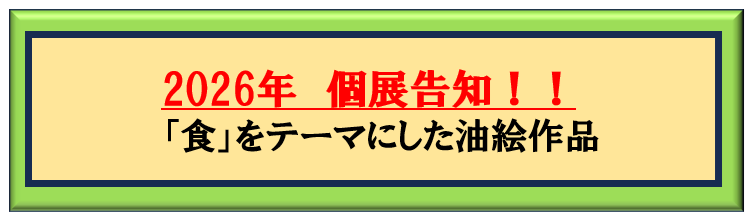
ご閲覧頂きありがとうございます^^
油絵画家の中西宇仁です。
今回は、絵画のタイトルの付け方、考え方や伝わる印象をお話していこうと思います。
絵画のタイトルは、作品の印象や世界観を大きく左右する重要な要素です。
作品を見る人との最初の疎通です。
言い換えれば作品の顔のようなものですね。
自分の作品の世界観を補足し記憶に残る手助けにもなるタイトルをしっかり決める事で他の作品に埋もれない確かな存在感を残せます。
ぶれない作品を残す為のタイトルの生み出し方について!
目次
【 厳格なルールはない 】
極端な話をすると作品タイトルに必ず守らなければならないルールはありません。
正直、タイトルはなんでも良いです。
作品によっては「無題」とタイトルを付けない場合もあります。
言語、数字や記号などあらゆる形式で表わせます。
ただ、展示内容によっては社会性との繋がりでNGとなる場合もありますがタイトルの付け方は作家の権利なので身構えずに考えていきましょう^^
【 タイトルをつける前に 】
タイトルはその作品の世界観や印象を定める重要な部分です。
安易なタイトルにしてしまうとせっかくの作品の魅力も半減です。
そこでタイトルを決める為に考えておくと良い事があります。
●何を伝えたいのか?
作品を通して自分が何を表したいのか?伝えたいのか?という制作するにあたり根本的な部分を掘り下げてみましょう。
作品を形成する根っこの部分は心臓部のような部分です。
その部分をタイトルとして表す事で作品に対する理解度を高められ観る人の共感性を得られます。
僕もタイトルを決める時は、自分が表したい要素をキーワード化して決めていますね。
展示会などで作品の紹介をする時にも背景と混ぜ合わせると驚かれる事が多いですね。
「~~があり、〇〇というタイトルになります」のように説明すると「なるほど!そういう事なんですね!!」と鑑賞者さんの目がぱっと開きます。
抽象要素のある抽象画や半具象画では内面性を押し出したタイトルが多くイメージしやすいですね。

●描いた動機
タイトルを検討する時に参考となるのがなぜその絵を描いたのか?という動機も有効です。
その作品を描く場合、何か描きだす為のキッカケや感情、考えがあり動き始めます。
水面下に潜む部分ではありますがシンプルでわかりやすいタイトルに繋がりますね。
作品を紹介する時にこの動機は、作家自身の背景に触れるので人柄や内面性に触れるので鑑賞者との話の幅を広げる事が出来ます。
作品は人と同じで見た最初の印象だけでなく理解を深める事で観方や感じ方が変わっていきます。
タイトルをキッカケに深い共感性を広げていけるようになります!
●注目してほしい要素
タイトルは内面性から決めるだけでなく色や形、キャンバス上に置かれるモチーフなど目に映るモノからでもつけられます。
色を主張したければ色に絡んだタイトル、シンプルな形状であれば形を主張させたりモチーフをタイトルにする場合ですね。
静物画や風景画など具体的な具象表現のある作品が多いです。
作品は観る人の状態によって観方や感じ方が変わります。
疲れている時に複雑な意図を含んだタイトルを見るとごちゃごちゃする事もあれば難しく考えない単純なタイトルにする事で抵抗感なく受け入れられる事もあります。
タイトルは作品の世界観、価値観など抽象的な要素をわかりやすく形として表す物です。
限られた範囲の中で記すものですがその存在意味は大変大きく影響します。
丹精込めた作品を損なわぬように考えてみてはいかがでしょうか♪

【 タイトルのパターン 】
タイトルはシンプルな文章、キーワードから組み立てていきます。
言葉の組み合わせを意識する事でばらつかないまとまったタイトルとする事ができます!
いくつかパターンを紹介しますね。
●内面性
感情や心象など内面的な要素をタイトルにする場合は抽象的な部分とストーリー性を意識してみると面白くなります。
例えば財布を無くした心境を現わした絵なら気持ちが下がる所から「不安と焦り」のように不安という心境と焦りという様子をつける事でイメージが湧いて来るかなと思います。
「心境+様子」のように複数の要素を内面性と組み合わせる事で作品への共感性を手助けできます。
●写実性
リアリティある物体や構造体などがあればモチーフの種類と色や状況を組み合わせる場合です。
例えば、リンゴの作品あら「赤い林檎」のようにモチーフと色を組み合わせる。
雨が降った後の道を描いた絵なら「雨上がりの道」など環境と道というモチーフを組み合わせてみるなどこれも複数の要素を写実性と組み合わせてタイトルを決められます。
●その他
絵で表したいものをタイトルにするなら物語性を持たせてみると良いでしょう。
詩を歌う感覚に近いですかね。
僕の場合、タイトルには物語性を持たせる事が多いですね。
詳しくは作品集で詳細な内容を載せているので一緒に読み合わせてみてください^^
他によくあるのが英語などの外語語や造語を使うタイトルですね。
ただ、僕の場合知識が足らず英語タイトルだと読み切れない事があります・・・
ただ、意味は似ていても日本語とは違うニュアンスで受け取れるのでそれ故に作品への印象も変わりますね。
●タイトルの印象例
1つ例として、文章の組み方で変わるタイトルの印象を見て見ましょう。
林檎の絵に対し、「林檎の赤」と「赤い林檎」2つのタイトルを見て何を感じますでしょうか?

僕なら前者の林檎の赤だと赤を主張した抽象的な作品で後者の赤い林檎は静物的な赤い林檎の絵だなという印象です。
もう1つ例として、光をテーマにした作品で「沈黙の光」と「光の沈黙」というタイトルがあるとします。

沈黙の光というタイトルだけで見ると暗闇の中に小さな光が一筋あるイメージが湧き、光の沈黙というタイトルだけで見ると神々しく光っていた光が消えていく切なさを感じますね。
このように一見同じようなタイトルでもワードや文章の組み合わせによって印象が変わるという事も意識してみると良いかなと思います^^
【 タイトルを決めるタイミング 】
絵のタイトルはタイミングによってその時々で決める、または見直すと整理されます。
絵の制作中に内容が整理されそこで決めるのも良し、絵を描き始める前の構想の段階で先に決めてしまうのもありです。
制作中は、進めて行くに連れて作品の完成度が高まってくるのでより明確なイメージを持ちやすくなります。
絵を描き始める前の構想では、絵の設計や整理を事前にする事で煮詰められるのでそこで決めてしまう事も可能です。
(絵の設計についてはこちらでご紹介しております!)
すぐに決める必要もないので一度決めた後に日を置いて見直す事で感覚がリセットされるので客観的に見直す事も出来ます。
冷静に見ると最初は良かったと思っていたことがイマイチに感じたりと冷静な判断で見れます。
いくつかタイトル候補を残しておけば組み合わせたり良いタイトルを絞る事も出来ますね。
作品が完成した後にいきなりタイトルをひねり出そうとしても難しいのでこのようにタイミングに合わせて練っていくと決めやすくなります!
【 タイトル決定のちょっとしたコツ 】
複数の作品を平行して制作していくとそれだけタイトルを決めていく事となります。
展示会や納品などなるべく時間を削減させたい事もあるかと思います。その時にタイトルを決める時間を減らせられたら良いですよね。
その時にテンポよくタイトルを決める方法として統一テーマを意識したタイトルの決め方があります。
作品によっては共通のテーマを分けて描く事もあるのですがこのシリーズ性をタイトルに合わせると決めやすくなります。
例えば僕の場合ですと食を共通のテーマにしていくつかの作品に分けた食シリーズ作品があるのですが関連した要素を紐づけていくと決めやすいです。
こちらの作品はイクラを共通テーマとしているのですが3作品に「命・造・育」と関連性をつけています。
そうする事でタイトルの構成としても統一性を持たせられるようになります。
他によくあるのは数字で分けるタイトルの付け方ですね。
「〇〇Ⅰ、〇〇Ⅱ、〇〇Ⅲ」のように〇〇を共通名にし数字で分ける構成です。
シンプルで関連性を持たせられるタイトルの付け方ですね。
タイトルの決め方は自由ですが個人的にこのタイトルの決め方は避けたいなと思う事をお話したいと思います。
●説明しすぎない
具体的な内容をタイトルにするとそれが説明しすぎてしまいます。
例えば3本の桜の木が描かれた作品に対し、「公園に咲く3本の桜の木」というタイトルと「公園の桜」だとどちらがしっくり来るでしょうか?
僕なら公園の桜というタイトルの方が良いかな~と思います。
タイトルは絵の世界観をコンパクトにまとめた表記でもあり作品に対して創造性や感情度を膨らませます。
前者の様に説明チックなタイトルになると「そのまんまじゃん」と好奇心が削がれてしまう場合もあるのでかみ砕きしすぎないタイトルが良いですね。
タイトルを見て、「何だろう?、何でかな?」と想像力を働かせられるような組み方が良いですね。
●意味不明しすぎない
タイトルを読んでまったく理解できない、引っかからないワードは観る人が置いてけぼりになります。
専門的な知識や言語などのワードだと知っている人なら繋がりやすいですが全く知らなければ意味不明のまま終わります。
お仕事の場でも人を何かの役割や業務に配属させたり割り当てるときに「Aさんを〇〇へアサインする」と言われてもアサインの意味を知らなかったら「へ??」ってなります。
アサインの意味を知らなくても「Aさんを〇〇へ配属します」と言えばAさんには伝わります。翌日から間違えずに配属先へ向かう事ができます。
タイトルも同じで見る人に通じない、共感性がないと伝わらないというわけです。
ただ、これらは観る側の見聞や傾向にもよるので一概には言えない所もありますね。
作品制作に比べてタイトル決めに大きな労力は必要ありませんがちょっとした組み合わせで作品の印象を左右します。
それをお披露目の場で掲示するわけですからね。
また、展示会で置く作品キャプションの作り方についてはこちらでご紹介しております!
いかがでしたでしょうか?
タイトルも掘り下げていくと細かい所ですが作品への印象や理解度を左右させるデリケートな部分です。
人で例えたらキラキラネームをつけられて老人になってもその名前で生き続けるわけですからね。
自分の作品を活かしたいと思うのであればタイトルにも意識を集中させて掘り下げて真の名前を授けてみてはいかがでしたでしょうか^^
話は変わりますが展示会などで作品の魅力や情報を効果的に伝える方法なども限定してお届けしております。
無料で電子書籍もございますのでお気軽にご覧ください^^

オンラインを活用したマンツーマンでの絵描きサポート
などもご提供しております。
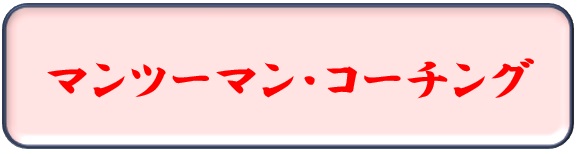
また無料相談も受け付けておりますので
些細なお悩みやご質問などお気軽にお問合せ
ください!
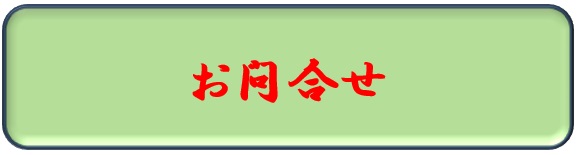
最後までお読みくださりありがとうございます^^
少しでも絵のお悩み解決に繋がりますように♪












コメントを残す